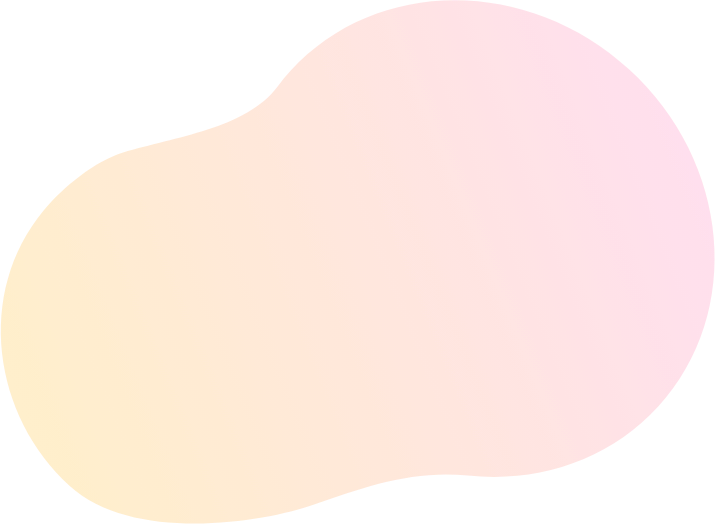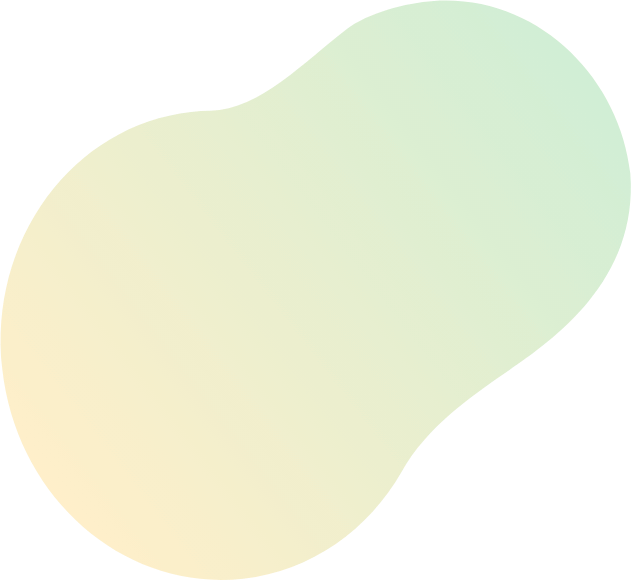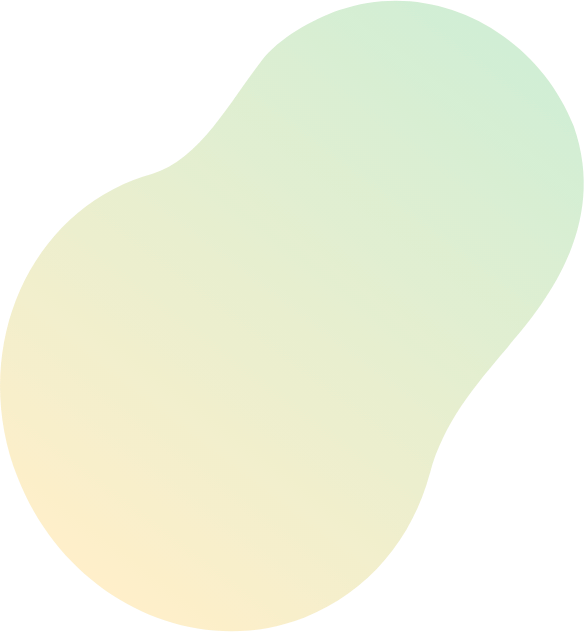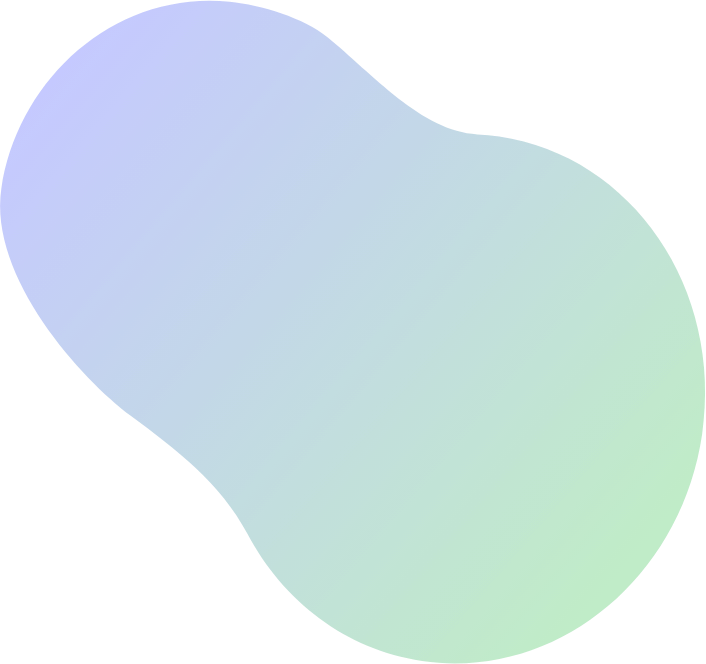お話しいただいた方
大東建託株式会社 ダイバーシティ推進部
部長 福永 智子 様(写真中央左)
課長 新関 晶久 様(写真左)
チーフ 樋口 三希子 様(写真右)
小森 亜季 様(写真中央右)
水戸川 くるみ 様
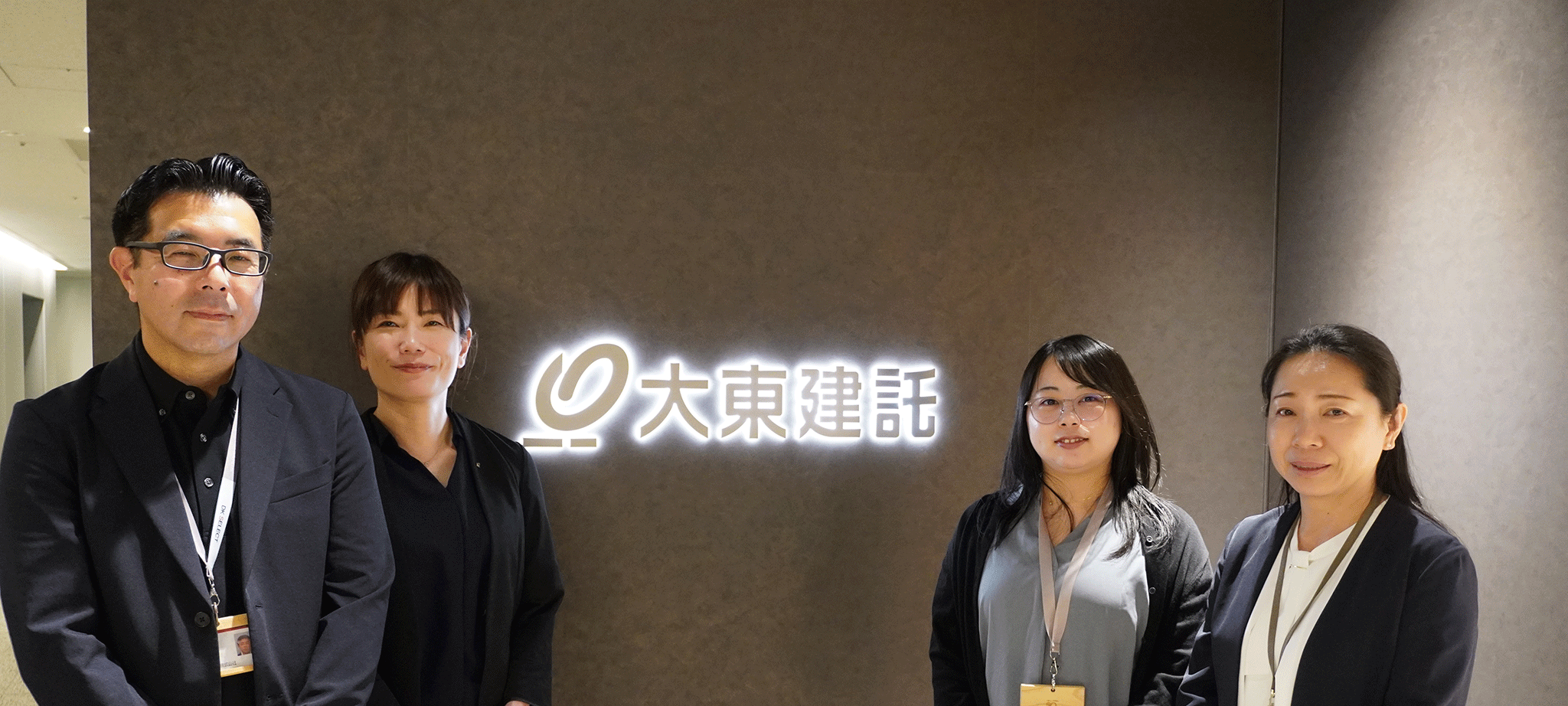
大東建託株式会社
賃貸大手の大東建託株式会社は、「みんなの個性を、会社の力に。」をテーマにダイバーシティの推進、LGBTQに関する施策を積極的に行い、PRIDE指標において2年連続でゴールドを取得しています。誰もが働きやすい環境をつくり、未来につなげる取り組みについて伺いました。
大東建託は「我が社は、限りある大地の最有効利用を広範囲に創造し、実践して社会に貢献する」を経営理念に掲げ、1974年に創業しました。最初は事業用の倉庫、建物から始まりましたが、時代の変化に対応しそこから居住用の賃貸事業へ転換していきました。アパート・マンションなど賃貸事業の提案から設計、施工および入居者斡旋、管理まで、一貫したサービスとなる「賃貸経営受託システム」を導入したことにより持続的に成長をしています。
オーナー様や入居者様のご要望や人生に寄り添いながら、託されたものを形にしようと従業員一丸となって取り組んできましたし、これからも次の世代や未来へとつなげていくことがとても価値あることだと考えています。
大東建託グループ全体のパーパスとして「託すをつなぎ、未来をひらく。」を策定しています。今後も事業活動を通じて、社会に貢献できるように取り組んでいきたいと思います。
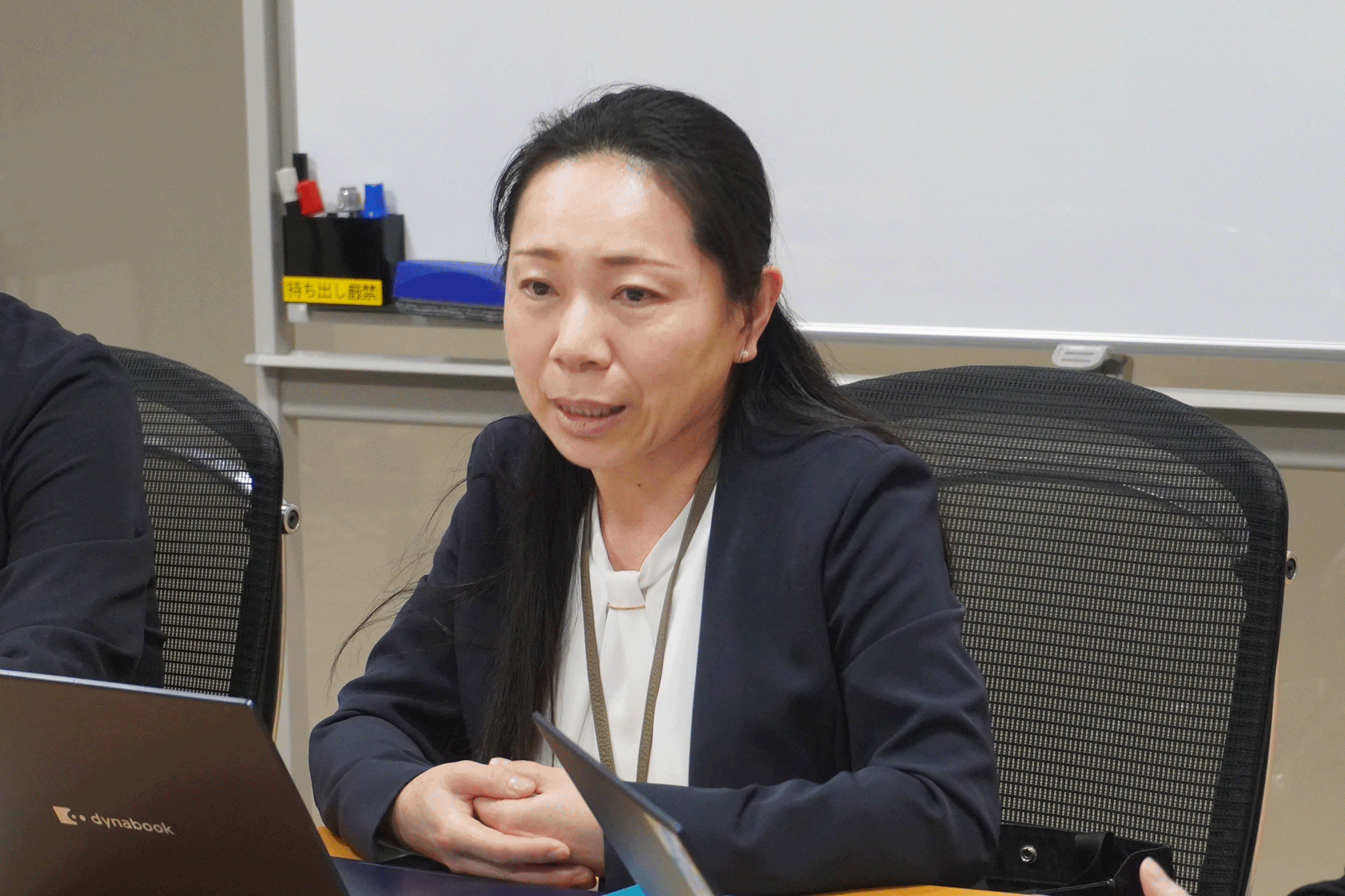
2015年、人事部傘下にダイバーシティ推進課を新設したのち、2022年にはダイバーシティ推進部とする組織改編を行うなど、経営戦略としてのダイバーシティ推進スタートから今年で10年目になります。「みんなの個性を、会社の力に。」というテーマで当初から女性活躍推進の取り組みを行っていましたが、取り組みを進めていく中で男性の育児休業や介護の問題など女性の活躍を推進するだけではダイバーシティとして十分ではないと思うようになりました。LGBTQの当事者は13人に1人の割合で存在するそうですので、女性活躍と同じぐらい重要な問題です。改めて検討してみると、弊社では今までLGBTQについて目立った施策を行っていませんでした。まずはできることから取り組んでいこうと2022年、トップメッセージを発信して、「いかなる従業員も受け入れて全員が活躍できる環境を作っていく」という取り組みを始めました。
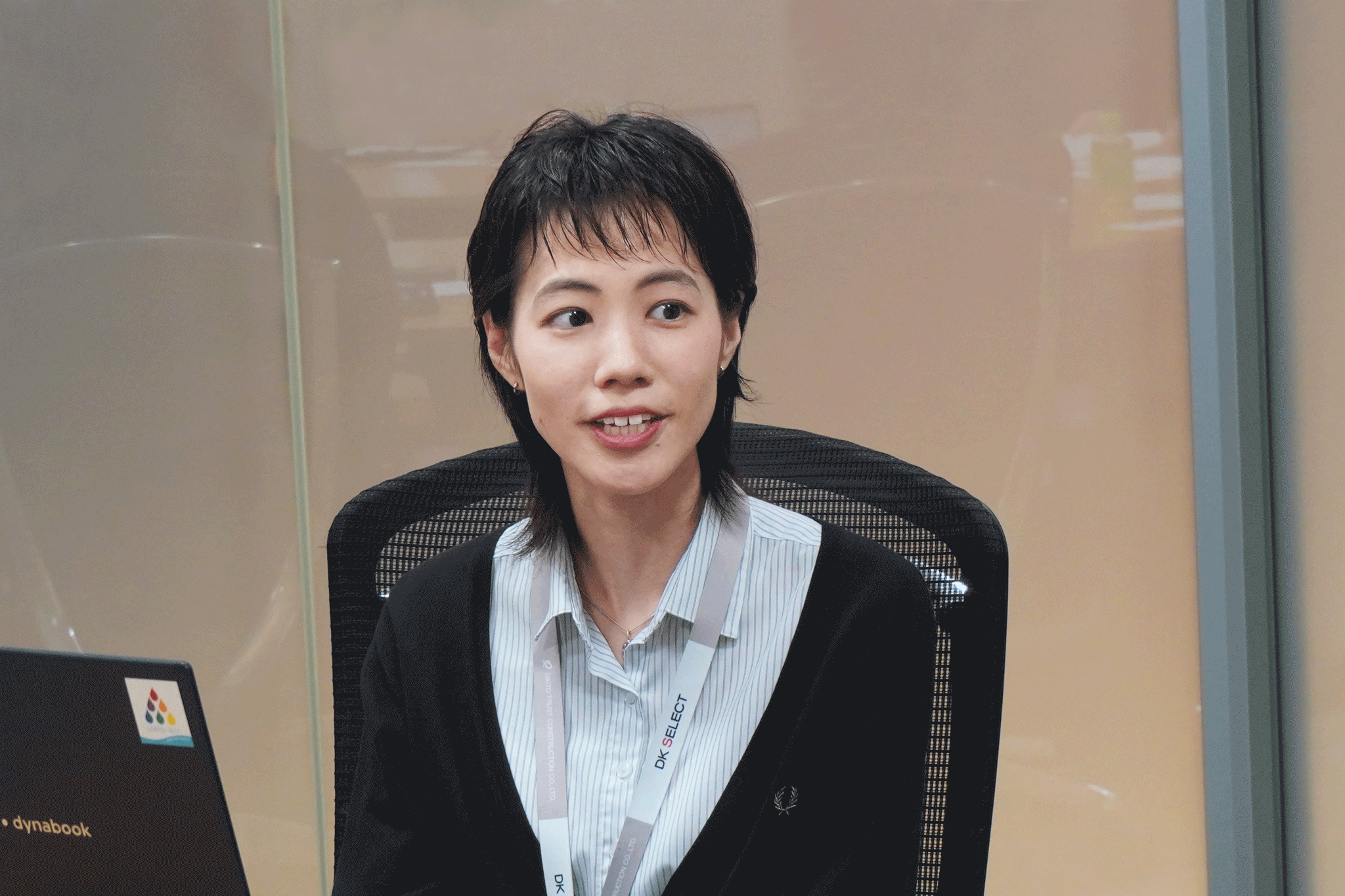
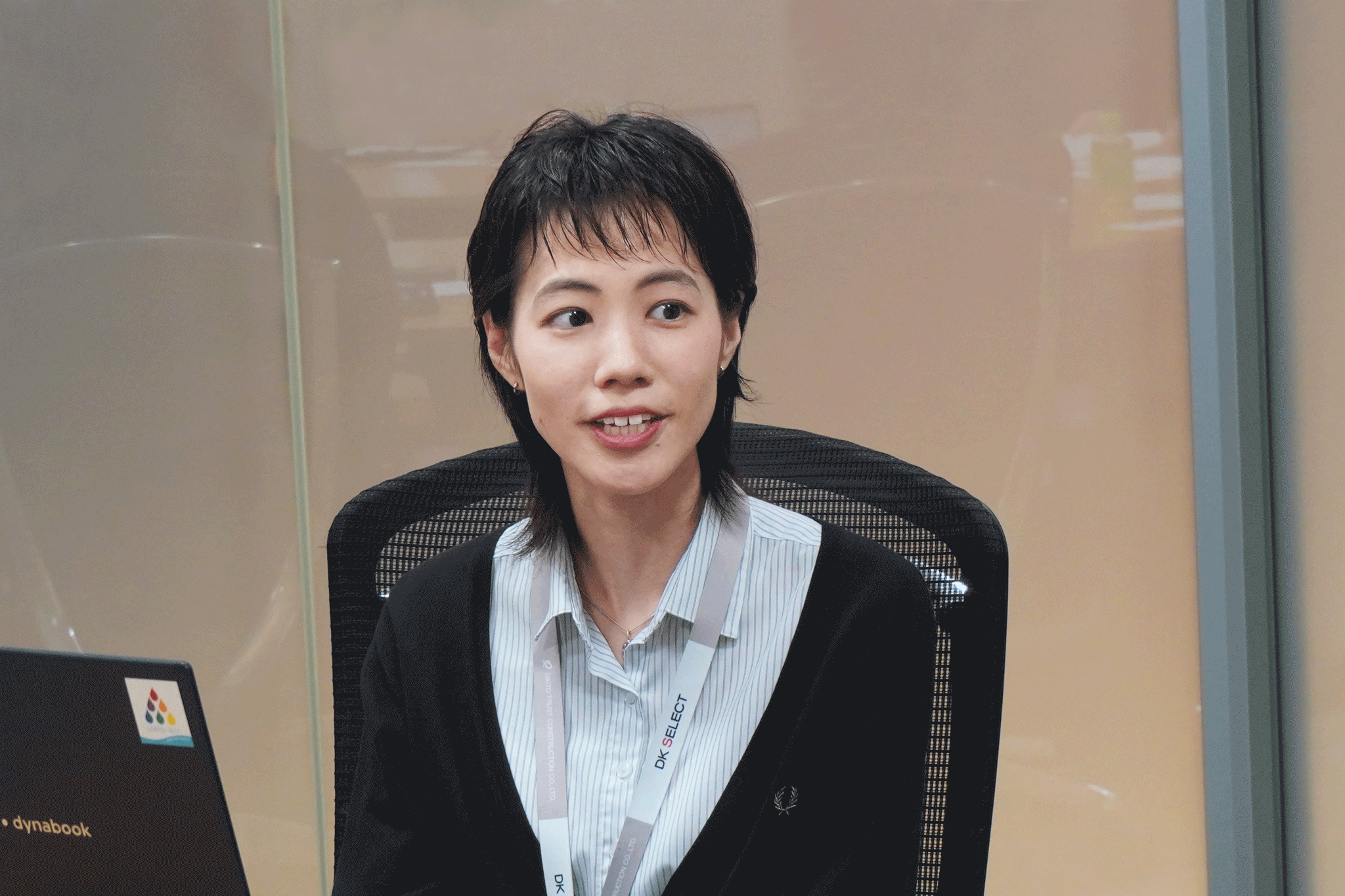
2020年に社員の行動基準となる行動規範を一部改訂し、性的指向・性自認に関する差別的な言動を行わない事を明記しました。2021年に性的マイノリティに配慮した社内制度として、戸籍以外の氏名を仕事で使用することができる「ビジネスネーム」、社員の同性パートナーやパートナーの家族にも福利厚生制度を適用することができる「ファミリーシップ制度」を導入しました。また同年全社員に向けてLGBTQへの理解を促すダイバーシティ研修を実施し、社員向け相談窓口の設置も行いました。
しかし、ハード面の整備だけでは当事者が働きやすくはなっても、すぐに心理的な負担の軽減にはなりません。まずは気持ちを共有できる場所が必要なのではないかと考えました。そこでLGBTQの理解者を社内で増やす取り組みとして当事者とアライによる社内ネットワーク「KENTAKU EST」を設立しました。

※写真は大東建託株式会社様にご提供いただきました。
LGBTQアライの社内ネットワークである「KENTAKU EST」では、メンバーが業務時間内で集まって、四半期に1回程度、ミーティングを行っています。内容はLGBTQ関連の情報交換がメインとなっています。設立当初は少人数から始まったコミュニティでしたが、現在は徐々にメンバーの数も増えてきています。
さらに今年度は、「KENTAKU EST」メンバーのアイディアを取り入れながら、ステッカーを作成しました。メンバーもアイディアを出し、楽しみながらデザインの作成ができました。6月のプライド月間に合わせて全社に向けた研修を実施し、研修をきっかけにアライとして賛同してくれた従業員へこのステッカーを配布しさらにアライの輪を広げていきたいと考えています。
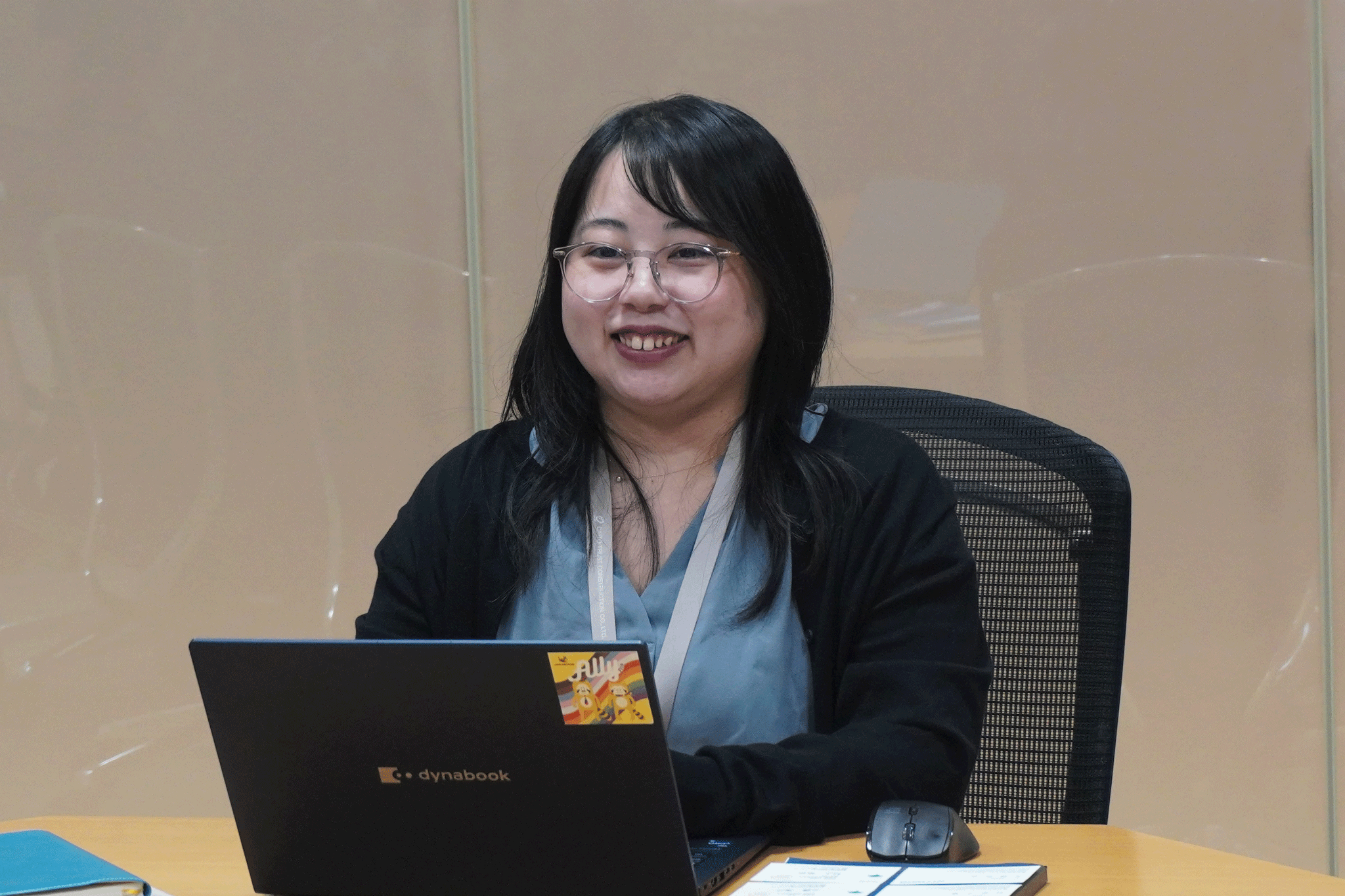
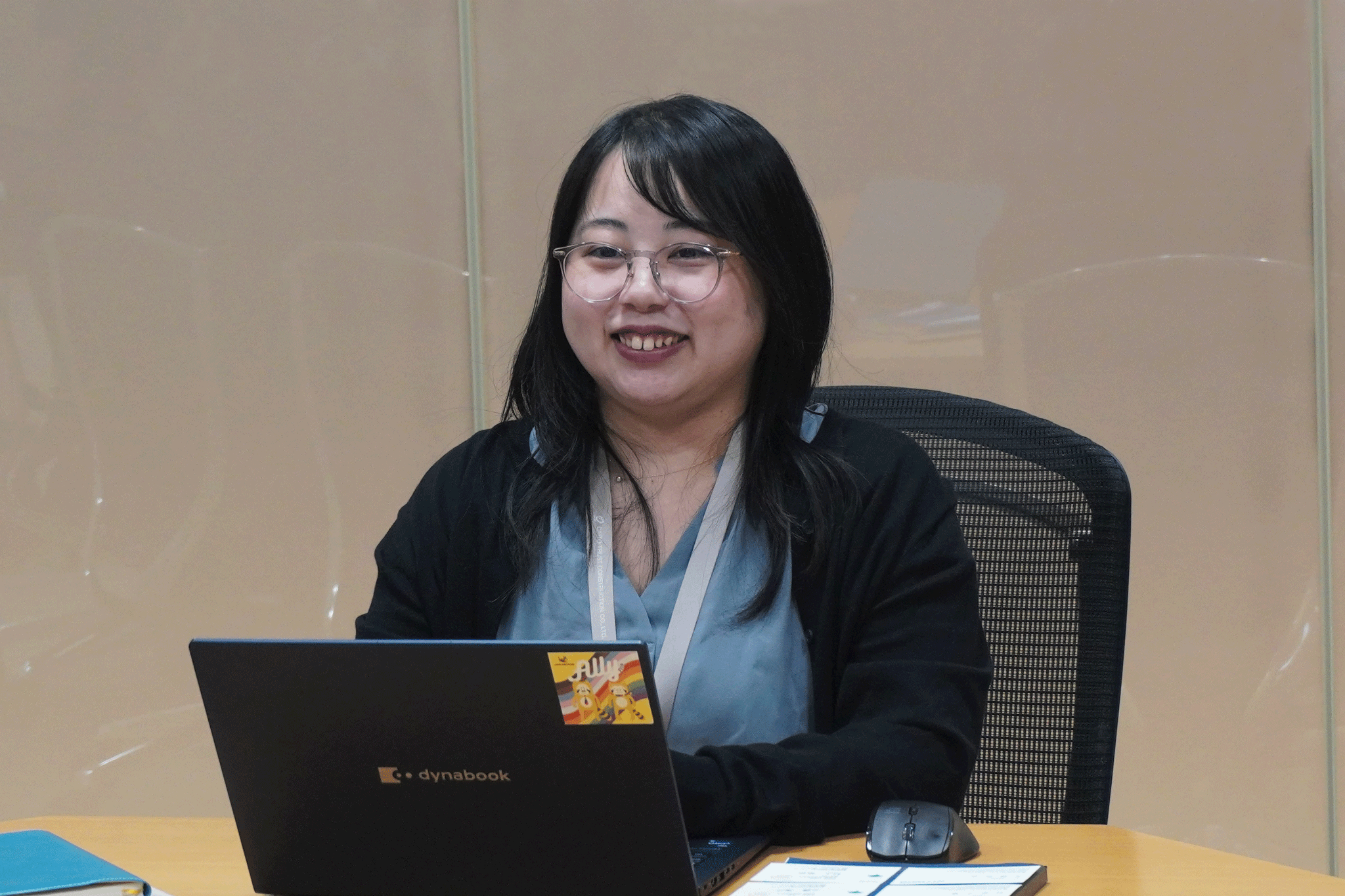
制度としてはしっかりしたものが作れたと自負していますが、なかなか社内の認知が広がらず、まだ全体的に利用者の数が少ないのが現状です。当事者の方にとっては、レインボーのグッズを身に着ける等して支援者の存在を認識できるだけでも、安心感につながると伺っています。今回のステッカー作成などの取り組みを通じて、社内にいるアライの存在を「見える化」していきたいと考えています。弊社は約8000人の社員がいますが、その中に支援者がいるということが当事者の方から認知できるようになれば、安心して制度を利用できるようになるのではと期待しています。
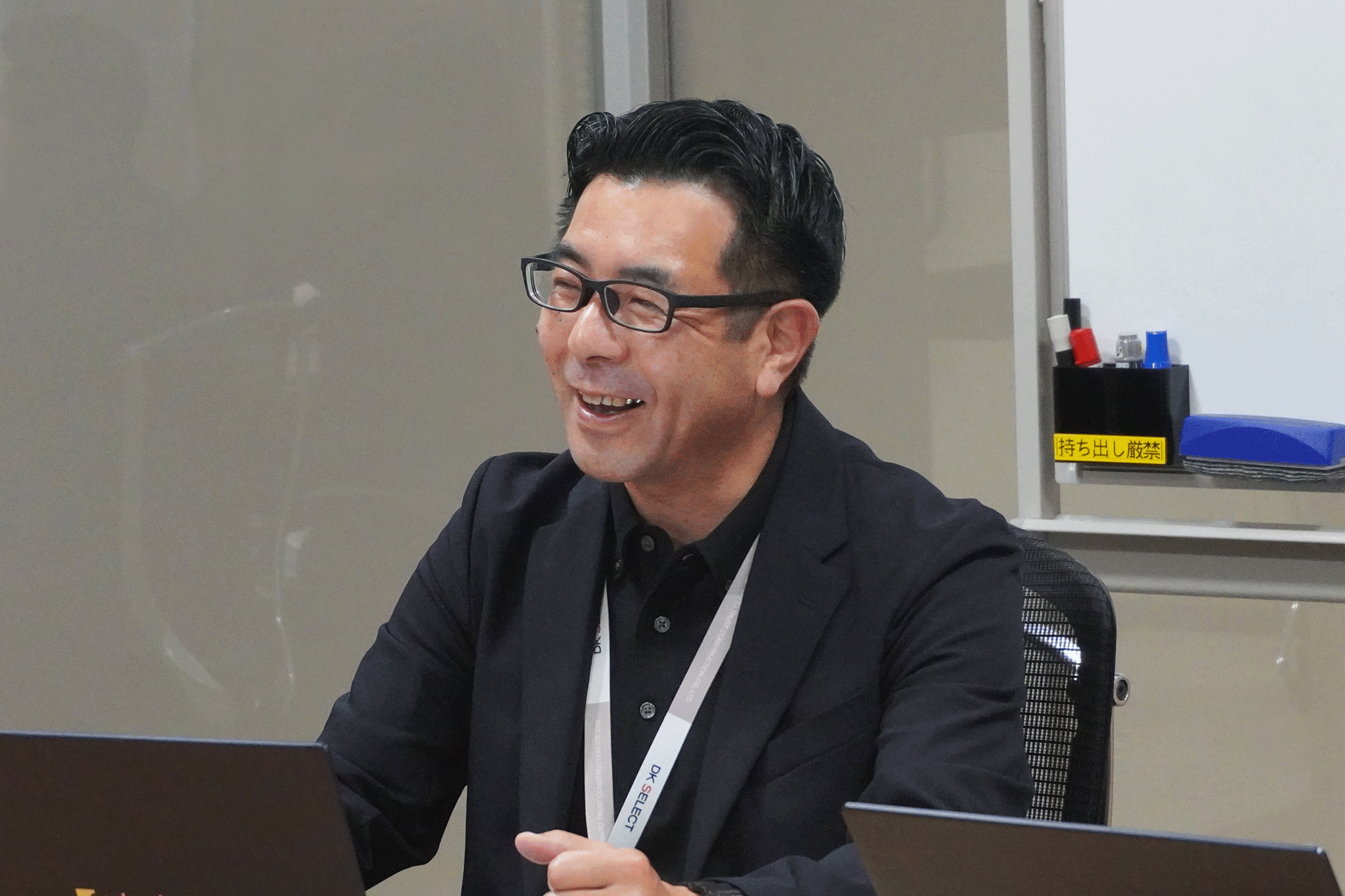
「KENTAKU EST」をはじめとしたアライコミュニティの取り組みをより活性化させて、社内全体の意識を変えていきたいと思っています。社内では研修などを実施しておりますが、LGBTQに関する知識やコミュニティについて、社員からは「意外と知らないことが多かった」という意見があります。
現在は働く環境を見直し、LGBTQを正しく周知する取り組みをしています。今後はアライの概要が一枚で分かるようなチラシを作成する等して、社内周知を図ることを検討しています。社員一人ひとりが個性を尊重し、多様な人材が活躍できるように推進していきたいと思います。
私自身も今回作成したグッズを使用したいと思います。そして、そのグッズを見た人がLGBTQに関心を持ち、取り組みや制度が認知され、社員全員が安心して活躍できる会社にもっともっとしていきたいです。
賛同の気持ちを持っていたとしても、目の前の業務が忙しくなるとそれ以外の事に目を向ける余裕が無くなることがあります。
ですので、1回の告知だけで終わらず、様々な方法で周知していくことが非常に重要だと考えています。社員への研修でLGBTQに対しての正しい知識を持ってもらうことももちろんですが、ストラップやステッカーで意思表示をする取り組みをどう広げていくか、考える必要があると感じています。
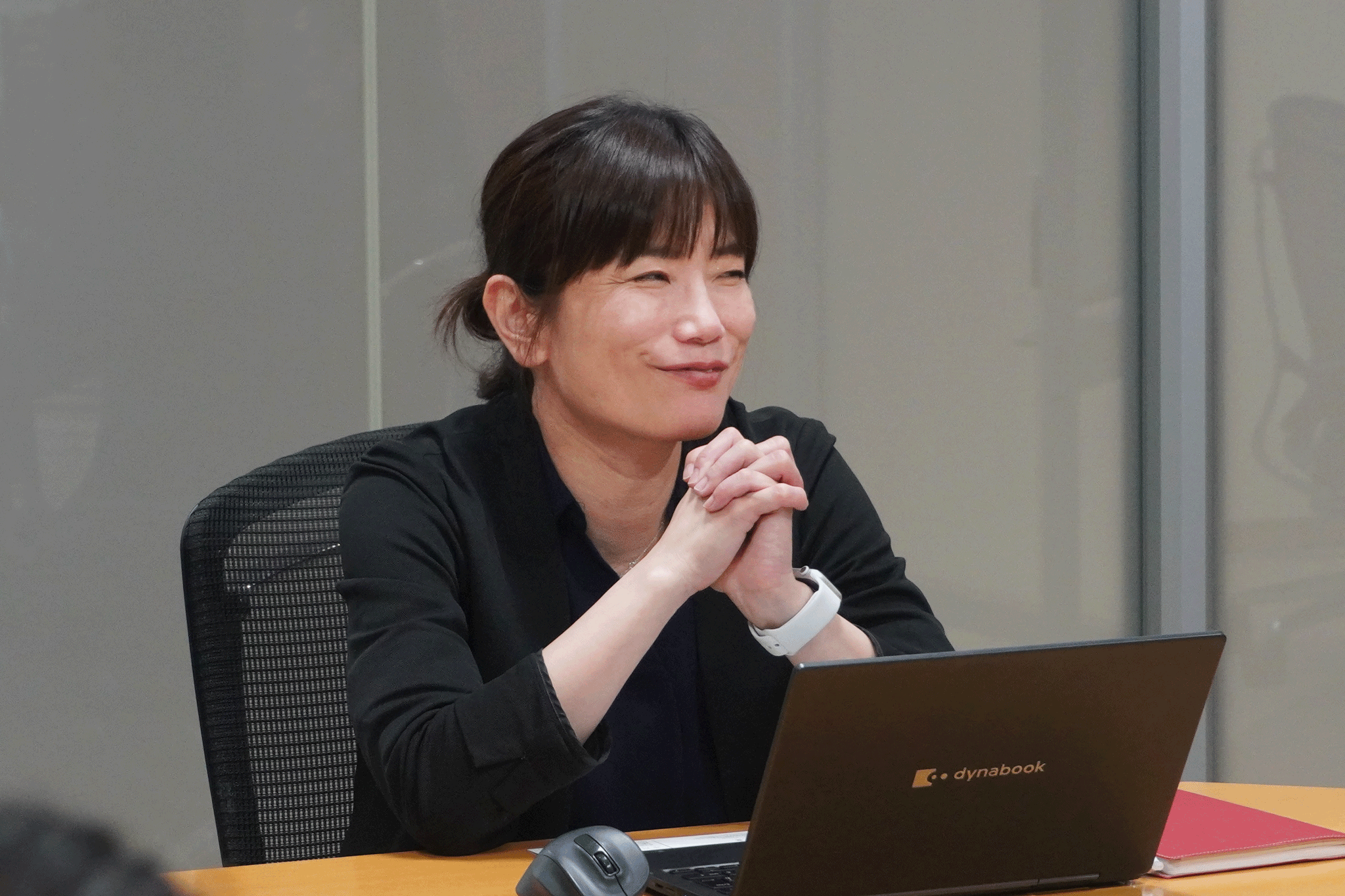
「制度だけでなく、気持ちを共有できる場づくりを」という想いから立ち上げられたアライコミュニティ「KENTAKU EST」。ステッカー作成などの取り組みを通じて、LGBTQへの理解は着実に進んでいるのではないでしょうか。さらに可視化し、輪を広げていく取り組みを継続していただきたいと感じました。
東京都では性的マイノリティの方々が働きやすい職場の環境づくり等の取組
を支援するため、事業者の方へ向けた支援を御用意しております