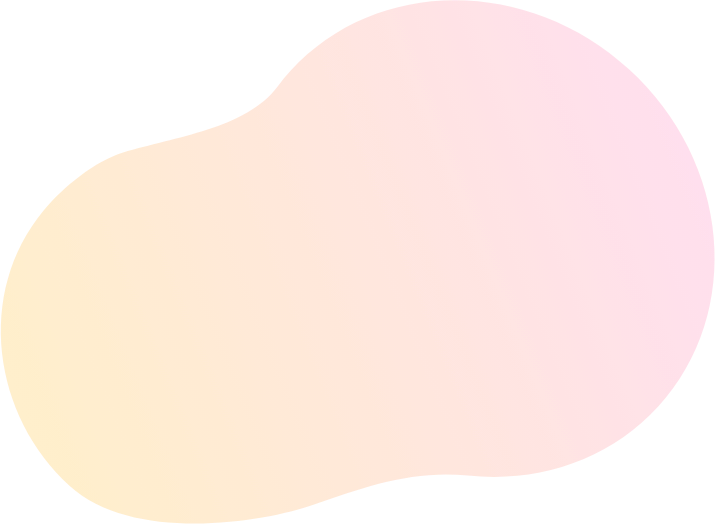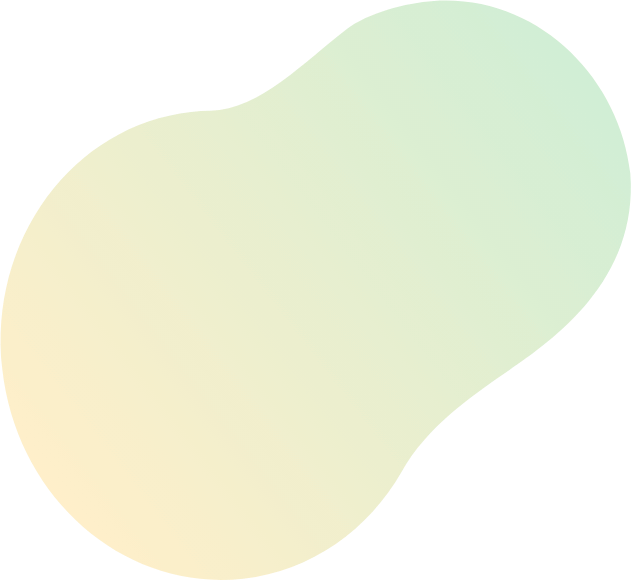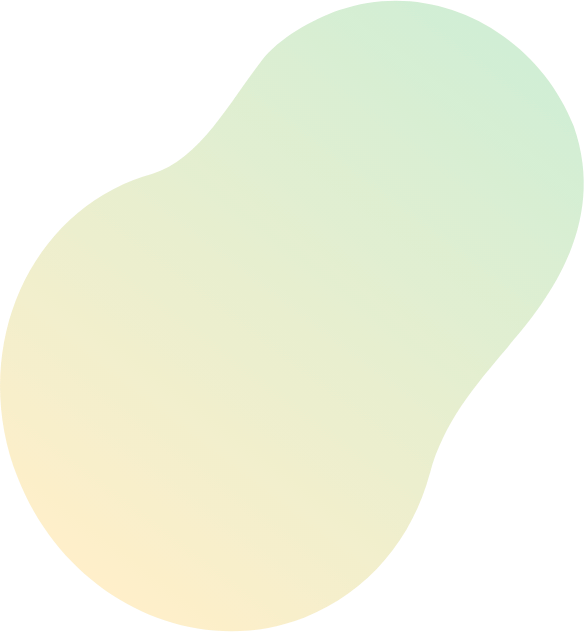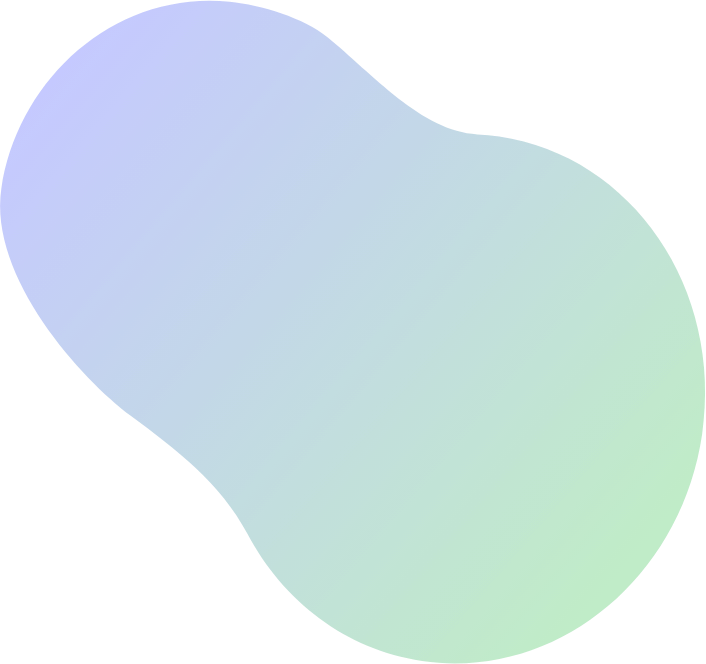お話しいただいた方
人事総務本部 ダイバーシティ推進センタ
センタ長
金森 さつき 様(写真中央左)
人事総務本部 労政部 労政グループ
主任 森 亮輔 様(写真左)
スマートライフソリューション事業部
企画部 担当部長
橋本 和広 様(写真右)
ITプラットフォーム事業部
デジタルプラットフォーム本部
事業戦略グループ 主任技師
佐藤 千文 様(写真中央右)

株式会社日立ソリューションズ
日立グループのデジタル事業をけん引する株式会社日立ソリューションズは、社内のアライコミュニティと連携した取り組みで、LGBTQ+の支援において高い評価を受けています。
今回、LGBTQ+の取り組みを推進する、ダイバーシティ推進部署の方とアライコミュニティの方双方にお話を伺いました。
日立ソリューションズは、日立グループのデジタル事業をけん引する中核企業として、社会生活や企業活動を支えるさまざまなソリューションをグローバルに提供しています。そして高度な技術力で自社製品・サービスを開発するとともに、米国に拠点を設置し、世界中の最先端デジタル技術を積極的に採り入れています。
創業以来、従業員を最も貴重な経営資源と捉え、働き方改革やダイバーシティ経営、人財育成などに力を注いできました。当社の持続的な成長と、事業活動を通じた持続可能な社会の実現に向けた価値創造を実現するために、DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)を不可欠な要素と捉えて推進しています。


2009年からダイバーシティ推進の専任組織を設置し、働き方改革やダイバーシティ経営の一環としてLGBTQ+に関する全社的な取り組みを進めてきました。その中で、働き方改革のカウンシルメンバーを中心に、従業員有志によるLGBTQ+アライコミュニティが2017年に発足しました。会社の取り組みを加速するだけでなく、LGBTQ+の方が日々直面する職場にこそ、正しい理解を浸透させることが必要だという思いから、草の根活動としてLGBTQ+アライコミュニティの活動がスタートしました。ダイバーシティ推進センタもこの活動に共感し、LGBTQ+アライコミュニティの提言を取り入れながら、連携してLGBTフレンドリーに取り組むことになりました。
LGBTQ+アライコミュニティは、LGBTQ+などのマイノリティであっても「働きやすい職場とは何か?」を考え、社員同士が支え合うグループです。会社の経営理念に沿う形でミッション・ビジョン・バリューといった活動理念を掲げ、参加者の理解を促しています。業務外の自主的なコミュニティとして活動していますが、会社として取り組んだほうが良いことは、アライコミュニティから積極的な提言を実施しています。

私は発足当初から、橋本と共に、アライコミュニティで活動しています。
ダイバーシティに関わるようになったきっかけは、各事業部門での課題にどう取り組むべきかを考えたことでした。
当初の課題は女性活躍中心で、女性活躍ワーキングという活動を始めましたが、活動するうちにダイバーシティに関する感度が全体的に上がってきて、LGBTQ+にも目を向ける機会が増えていきました。
また、当時私が所属していた事業部門の女性社員の割合は8%でした。調査によると、LGBTQ+の人々の割合はおおよそ8%〜10%と言われており、事業部門の女性の割合とほぼ同じでした。このことから、女性活躍推進と同じくらい重要な取り組みであると気づきました。その後、事業を立ち上げる中でさまざまな人とコミュニケーションを取るうちに、実際にLGBTQ+の方が職場にいることを知りました。当事者の悩みや想いを直接聞いたことで、アライコミュニティを立ち上げる決意を固めました。
3人から始まったコミュニティは、現在7名の中心メンバーが活動を牽引しています。また、イベントなどに積極的に参加するメンバーはおよそ30名〜40名にのぼります。
ただし、会社側にはメンバーの名前を伝えないという約束をしています。これは、カミングアウトやアウティングにつながる可能性があり、心理的安全性を確保するためです。そのため、公に活動するメンバーの顔や名前は伝えているものの、それ以外の情報は公表していません。


実際に、アライコミュニティを立ち上げる前からLGBTQ+の問題に対して意識をもち、独自に活動していたメンバーもいて、その方々にも、会社でアライコミュニティを立ち上げることに賛同してもらい、中心メンバーに加わってもらっています。
アライコミュニティに参加いただくのはウェルカムですが、当事者の情報を扱う可能性もあるため、事前に誓約書をいただくことで、心理的安全性を確保するようにしています。
そのため、どんどん広げていこうというわけではなく、草の根的に活動しています。
当社では、従業員一人ひとりの多様な価値観が尊重され、誰もが能力を発揮して活き活きと働ける職場をめざしており、LGBTQ+関連でもさまざまな施策を行っています。
全従業員を対象に、eラーニングによる学習や「職場におけるLGBTハンドブック」の公開など、誰もが理解を深め、学べる環境を整えています。ハンドブックの作成にあたっては、記載内容が理解しやすいか、誤解を招かないかなど、アライコミュニティとも連携し、相互確認を行いました。
また、国内グループ5社の社員を対象に毎年開催しているダイバーシティイベントでは、アライコミュニティがLGBTQ+をテーマとする登壇者の企画を会社に提案し、2017年から継続してLGBTQ+に関する講演会を共同開催しています。
制度面では、2020年4月より、家族の定義に「同性パートナー」を新設し、休暇制度・各種手当・福利厚生サービスの利用において、配偶者と同じ扱いとする制度を整備しました。
職場環境面では、社内外の訪問者が誰でも利用できるオールジェンダートイレを本社に設置したり、自分らしく働くためのドレスコードフリー化を実施するなど、多様性に配慮した環境整備を進めています。こうした職場環境の整備においても、アライコミュニティの意見を取り入れ、実際の運営に生かしています。これらの取り組みが評価され、PRIDE指標において6年連続でゴールド認定をいただくことができました。(2025年2月時点)

アライコミュニティの活動としては、セクシュアル・マイノリティをテーマとする映画の鑑賞や意見交換会、書籍の読み合わせ会などを実施し、アライとしての理解を深めています。また、東京レインボープライド2024では、有志とともにフェスタやパレードに参加しました。
当社の社長も、法務省が進める「Myじんけん宣言」の中で、トップメッセージとして、人権尊重の方針や性別、性的指向、性自認等による差別や個人の尊厳を傷つける行為を行わない事などを宣言しています。


社長が全社員向けの説明会の場で、Hitachi Pride LogoのアライTシャツを着用して登壇し、アライの重要性について自らの言葉で直接メッセージを発信されたこともありました。当事者の方からは、とても励みになったというお声も聞いて、嬉しく思いました。
LGBTフレンドリーな職場風土を作ることをめざしていますが、全社レベルでの取り組みが主であり、現場レベルの日々のコミュニケーションまでは、なかなか施策が浸透しておらず、期待する効果が定着していないことが課題でした。
アライコミュニティ活動を始めた当初は、活動している方々の中ではとても有名な当事者の方に講演をお願いしたのですが、興味のない人からすると、知らない人がLGBTQ+について話すセミナーというイメージで終わってしまいます。
そこで、少しでも興味をもっていただくために、芸能人など、著名な方に登壇していただくセミナーを企画しました。この方が話すならちょっと聞いてみようという人もいるので、関心のない層に届ける方法の一つだと思っています。
2024年度の講演会では、講演会のテーマや内容も何度も打ち合わせをして、どうしたら自分ごととして考えてもらえるかというのを意識しました。
社外講師から、LGBTに関する基礎知識や、最新の法改正や判例動向についてご説明いただき、LGBTQ+の方に実際の体験を基に、普段直面している困難や、どのような配慮を嬉しいと感じるかを確認しながら、アライの重要性について学び、賛同者にはアライであることを表明するステッカーの配布を行いました。
オンラインで聞いている社員からは、講師の話に対して、たくさんチャットが飛んできて、心に響いたという声を多く聞くことができました。また、アンケートの自由記入欄にも多くの意見をいただきました。「LGBTQ+の方々に関する直近の判例などの詳細な部分までご紹介いただき、報道だけではわからない悩みや苦労を知ることができた」「講演をきっかけに、家族とも会話することができ、良い機会となった」「アライであることを表明するステッカーを貼り、寄り添っていきたい」といった感想が寄せられました。
ダイバーシティの講演会も7年連続でやっているのですが、毎回会社の幹部が出席して、熱心にメモをとって聞いていて、社長も役員陣もどなたに話を振っても答えてもらえることも嬉しく、アライだけではできないことだなと感じています。
社長自らが「初歩的なことでも質問していい?」と率直に尋ねたことで、社員からは「基本的なことを質問してもいいんだ」「自分も正しく理解できているか不安だったので助かった」といった声が寄せられました。こうした風土の醸成により、職場全体の理解促進が進んでいます。
また今年度は特に管理職の参加率が高く、組織全体としてLGBTQ+に関する意識向上が図られていると感じられました。管理職が積極的に学び、現場の理解を深めることは、企業文化の変革において重要な要素となります。
インクルーシブな組織風土の実現に向けて、LGBTフレンドリーな社員の裾野を広げることが課題です。これまで無関心だった層にも関心をもってもらえるような講演会や社外イベントをアライコミュニティと連携しながら企画・運営し、LGBTQ+に関する理解促進と、一人ひとりが自ら考える機会を継続的に設けていきたいと思います。
今後は、VRを活用した研修も検討しています。当事者の状況をVRで一人称体験することによって、もし自分が当事者の立場だったら何を感じ、どのように考えるのか?という想像力を養い、参加者同士で対話する研修ですが、VRの動画はもちろん、その後の対話において多くの気づきを得ることができます。VRというところをフックに、関心を深めるきっかけにできればと思います。
また、日立グループには、カードゲーム型の DEI 研修サービスを開発・提供している会社もあります。実は周りにもいるかもしれない多様な当事者の存在を知ることに始まり、日本で実際に起きたトラブルをもとに、難しい選択を迫られてしまう当事者のリアルな事情や困難を思い描くことができる内容で、ロールプレイとディスカッションを通じて学びが深まり、多くの気づきが得られます。当社でも、私やアライコミュニティのメンバーなどがこの研修を実際に体験しており、開発者を含む研修提供チームとは、今も日立グループ会社間の交流が続いています。
アライコミュニティの活動は草の根的にやっているため、ボランティアに近い活動になっていて、数は求めないと言いつつも、活動を広げていきたいという思いも強く、ダイバーシティ推進センタとアライコミュニティが協力して、全社にもっと発信していきたいと考えています。
講演会などの取り組みを社外にも共有し、LGBTQ+に真剣に取り組んでいることを公表することは、社会的に意義のある行動に繋がると考えています。
当社には、いろんなことにトライできる環境が整っているので、今後もさまざまな取り組みを行っていきたいと考えています。
ダイバーシティ推進部署やアライコミュニティ、グループ他社との効果的な連携が、経営層のLGBTQ+への理解も相まって、企業のみならず、企業グループ全体のLGBTフレンドリーな文化の醸成に大きく貢献していると感じました。今後も継続的に取り組み、社会全体に好影響を与えていただきたいと思います。
東京都では性的マイノリティの方々が働きやすい職場の環境づくり等の取組
を支援するため、事業者の方へ向けた支援を御用意しております